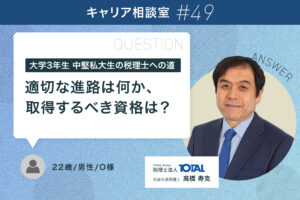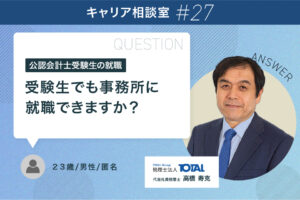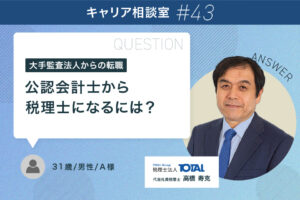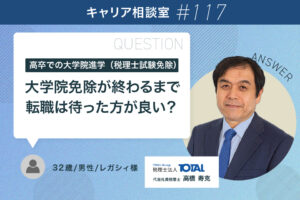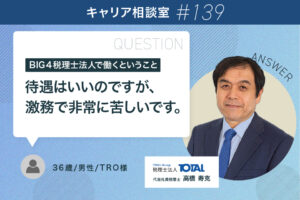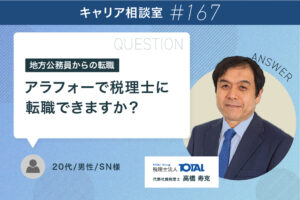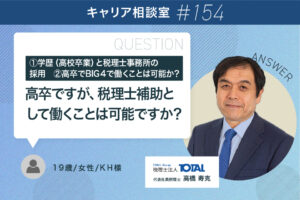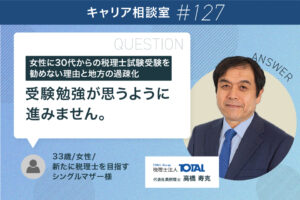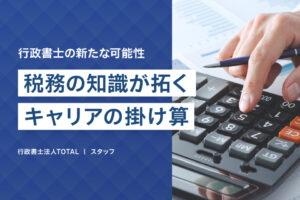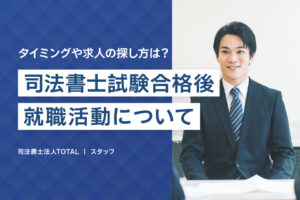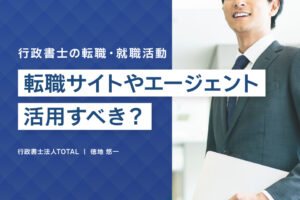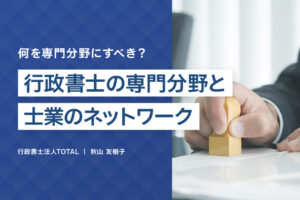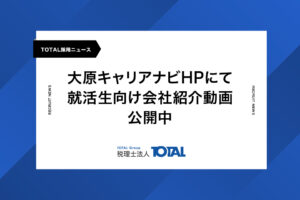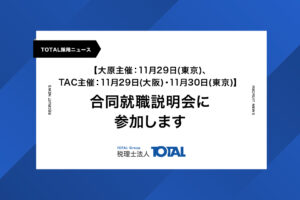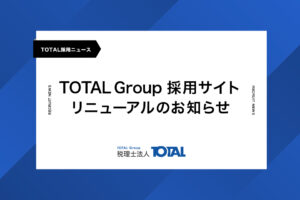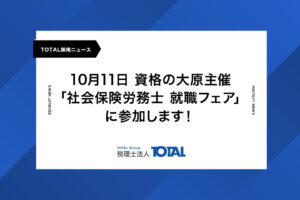キャリア相談室
所長の独断で後継者指名-今後どうすべきか?-
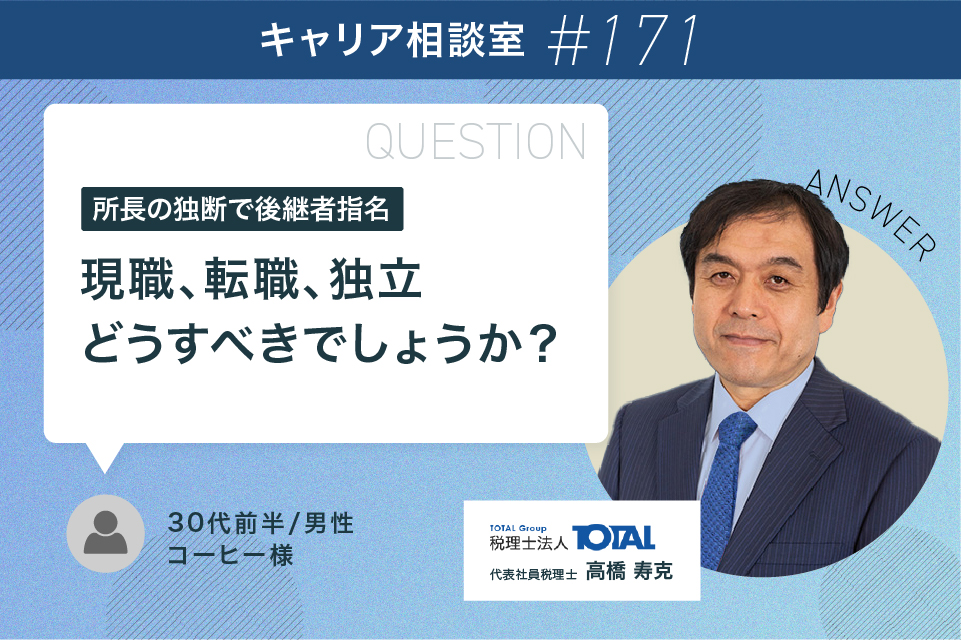
ご質問いただいた内容
相談者
名前:コーヒー
年齢:30代後半
性別:男性
資格:税理士試験3科目合格
学歴:簿記系専門学校、税法免除大学院
会計事務所経験:10年弱
相談内容
高橋先生、いつも的確なアドバイス拝見しています。私は、会計事務所経験10年弱、30代後半のコーヒーと言います。現在は税法免除通知を待っているところです。晴れて税理士有資格者となれる見込みが立った今、改めて自分の将来に悩んでおります。相談したい内容は、私にとって、勤務先を引き継ぐ、転職する、独立するの3つではどれがよさそうかという点です。
私の勤務先は、他の会計事務所と合併し形式上は税理士法人となりました。しかし、代表同士の関係は非常に悪く、実質は完全に別々の個人事務所のような運営が続いています。オフィスも別々で、向こうのスタッフの顔も知らず、法人化のメリットも感じられません。現在は裁判所で係争中で、税理士法人の解散はほぼ決定的です。
私が所属する事務所は、所長が80歳を超えており、後継者がいない状態です。社員パート合わせて10人未満です。顧客も高齢化が進み、顧問契約解除が相次いでいます。売上も右肩下がりのなか、所長とその家族に売上の40%〜50%が流れている状況です。
所長は、自分が1番でないと気が済まないタイプであり、自己主張が強いです。「勉強させてあげている」という感覚であるため残業代は払われず、給与水準はかなり低いため離職率は高いです。記帳代行がメインのアナログな昔ながらの会計事務所です。所長のチェックが適当なため、潜在的な税務処理リスクは相当にあると思います。
私は、大学院進学を決めた際、所長に「誰にも言わないでほしい」と伝えました。しかし所長は、私の了承なしに「後継者」として顧客に紹介し始め、知らぬ間に重い期待とプレッシャーを背負うことになってしまいました。環境を変えるリスクを避け、慣れた事務所で大学院に通うことを選びましたが、ずっと違和感を抱えてきました。
今後の方向性としては、以下の三択で揺れています。
- 勤務先の税理士法人を継ぐ
- 転職する
- 独立する
それぞれにメリット・デメリットがあるのは承知していますが、現状の経験やスキル、人脈、経済的なことを含めて、自分がどの選択をすべきか非常に悩んでいます。
高橋先生であれば、こういった状況の中、どのように判断されますか?
また、私の立場であれば、まず何から手をつけていくべきだと思われますか?
ご教授いただければ幸いです。
回答
転職か独立を勧めたい
コーヒー様、詳細なご質問ありがとうございます。税理士法人が、社員税理士の仲たがいで解散するというのはままある話です。社員税理士ではないのに巻き込まれる形となってしまったコーヒー様の心境、お察しします。
ご質問内容を拝見すると、コーヒー様が所属されている税理士法人の状況はあまり良い状態ではないと思います。今後の方向性として税理士法人を引き継ぐ、転職、独立の3点を挙げられていますが、私としては転職、独立を中心に検討した方がよいのではないかと思います。ただし、現職の税理士法人において在職証明書が取得できるかどうかは注視してください。
信頼関係が希薄なアナログ事務所を引き継いで幸せか
コーヒー様と、所長税理士との信頼関係はすでに希薄と言えるでしょう。コーヒー様から見た所長税理士は、税理士法人を維持できない、高齢で将来性が不安、利益を親族に分配、自己主張が強い、チェックが適当、コーヒー様のことを勝手に後継者に仕立て上げる―そういう方です。
質問文にあった「所長とその家族に売上の40%〜50%が流れている」というのは、具体的にどのような内容かは分かりませんが、所長の役員報酬の他にも、親族が経営する記帳代行会社に外注するとか、親族所有の土地建物に賃料を支払うといったことでしょうか。
雇用主と従業員は本来、一概に雇用主が「上」で従業員が「下」などは言えません。しかしコーヒー様の事例では、所長税理士は、年齢的にも経験的にも自分の方が「上」であり、コーヒー様のことをだいぶ「下」に見ているように思えます。コーヒー様の了承を得ない状態で顧客に「後継者」と伝えていますし、法律に反して残業代も出していないわけですから…。
慣れた事務所だからこそ大学院に通え、免除通知待ちの状況まで来られたことも事実かと思います。そういう面では恩を感じる部分もあるでしょう。しかし、所長税理士の親族に利益が分配される構造、残業代が出なくて離職率が高い労働環境、アナログな事務所をそのまま引き継ぐことが今後のコーヒー様の幸せにつながるでしょうか。私はその可能性は低いと思います。
残念ながらこのような状況は例外ではない
所属している税理士法人の状況をあまり良い状態ではないと書きました。しかし、税理士業界で特異的な事例・例外であるとは言えないと思います。税理士の仲たがいがあって税理士法人が解散しスタッフが巻き込まれることも、所長税理士が強烈な個性をもっていることも、アナログで属人的な経営をしていることも、親族を優遇していることもあります。
残念ながら、実質的に残業代を払わないところも耳にします。中小規模経営の税理士事務所は、他の中小企業と同じような状況を抱えることもあるということです。
コーヒー様の勤務先の問題は複合的なので、その点では珍しい状況かと思いますが……。蛇足かもしれませんが、中小会計事務所の跡継ぎ問題で、所長税理士の親族に税理士がいる場合、基本的にはその親族が跡継ぎとなる場合が多いです。
転職するなら標準化している税理士法人を第一候補に
転職するか独立するか、どちらがいいかはコーヒー様次第です。転職活動をする際には、どういった事務所かしっかり調べてみてください。30代後半で税理士もしくは税理士有資格者というのは、比較的転職しやすいはずです。もちろん色々な所長先生がそれぞれで経営されているとは思いますが、確率的には70代以上の所長先生の事務所は避けた方が、勤務する上での問題が起きにくいでしょう。
また、その事業規模も大きい方が望ましいと思います。今後独立するにしても、一度組織化・標準化している事務所で働いて、整備されたマニュアルやシステムに触れた方が、その後自身が経営者になったときに体制を構築しやすいと思います。もちろんいきなり独立するのも止めません。当初3年ほどは苦労するかもしれませんが、その後は安定するのが一般的です。
在職証明書を本当に発行してくれそうですか?
ただし、今の所長税理士が在職証明書を本当に発行してくれるかどうかはしっかり見極めてください。ご存じの通り、税理士登録するためには2年の実務経験が必要です。これを証明する在職証明書は、勤務先の、もしくは過去の勤務先の所長の署名・押印が必要です。円満退職ではなかった会計事務所の所長が、嫌がらせで、在職証明書にハンコを押さないといったこともあるようです。
コーヒー様の勤務先の所長税理士は、税理士法人解散に絡んで裁判で係争中とのことですので、その矛先が今後コーヒー様に向かうことも可能性としてはあり得ると思います。ここに懸念がある場合は、今の税理士法人で税理士登録してから辞めるか、場合によっては転職先でさらに2年働いてから登録するかを選ばなければなりません。
=================================
会計事務所を選ぶ基準の1つに「事業全てが見渡せるから小規模事務所で働く方が良い。会計事務所未経験者ならなおさら」というものがあるようです。私には、それが必ずしも正解ばかりだとは思えません。小規模事務所は相対的に、マニュアル化が進んでいなかったり、教育体制が十分でなかったりする事務所が多く、未経験者が働きにくいケースも見られるからです。
税理士法人TOTALは、税理士業務を産業化しようとしています。マニュアルとチェックリストを用意し、どこの事務所でも、どの担当者でも、一定の水準で決算書、申告書を納品できるようになる体制を整えています。また、DX推進の一環としてクラウド会計ソフトや自社開発の顧客管理システム、医療機関向けの独自クラウドシステム等を活用しています。Google Workspace EnterpriseおよびGemini Advancedを導入済みです。AIやITツールを活用して、より効率的に業務が行えるよう日々取り組んでいます。
お客様は一般法人だけでなく、資産家やドクターなど医療系のお客様も多いため、幅広く税務会計コンサルタントの経験を積むことが出来ますし、それぞれの分野に適した教育体制を用意しています。
=================================
執筆者

税理士法人TOTAL
代表社員税理士
高橋 寿克
千葉県船橋市生まれ。農家の12代目。税理士・行政書士・CFP®・医業経営コンサルタント。
開成高校、早稲田大学政治経済学部卒。
1999年 高橋寿克税理士事務所を開設。現在は全国17拠点に拡大したTOTAL Groupの代表として、税理士法人をはじめ、司法書士法人、社会保険労務士法人、行政書士法人を擁する。
徹底した業務の標準化やクラウドシステム(マネーフォワード、freee)活用で業務効率化を推進。「あなたと共に歩み、あなたと共に成長したい」を理念に日本一の総合士業事務所を目指している。