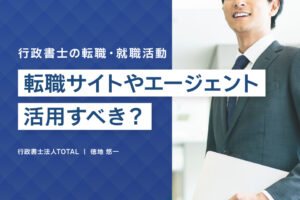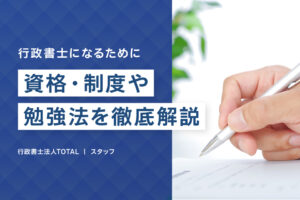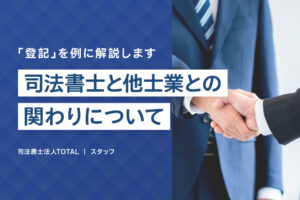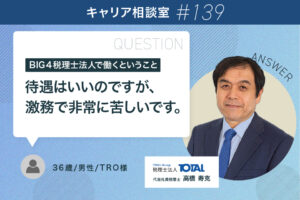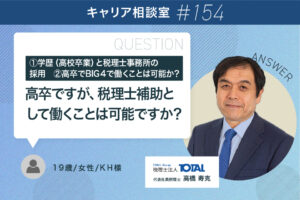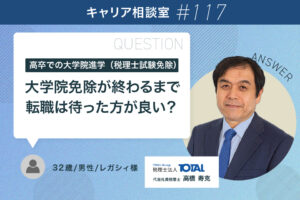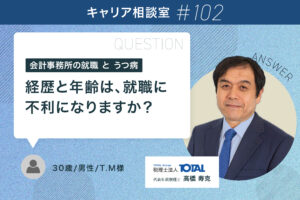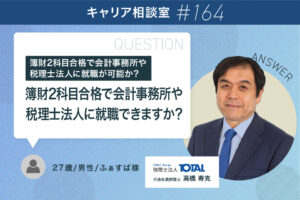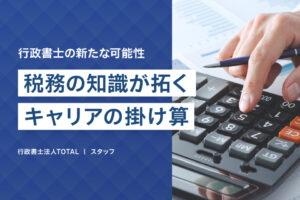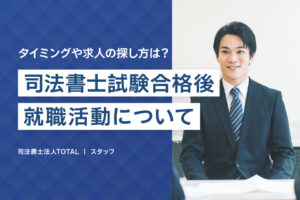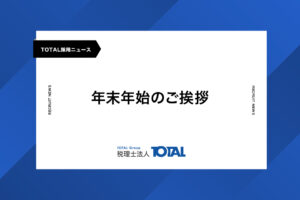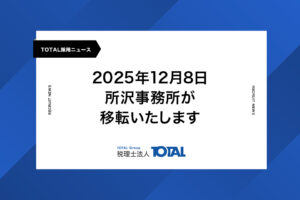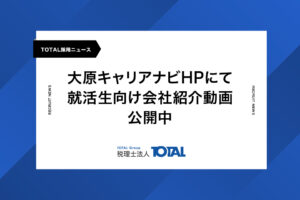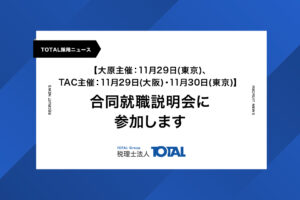キャリアコラム
行政書士試験合格後にすぐ独立すべきか、事務所勤務すべきか?

行政書士は、士業の中でも比較的独立開業しやすいと言われています。自宅を事務所として開業できる為、初期投資が少なくて済み、独立開業に関する条件は事務所の確保と事務機器類の準備、行政書士会への登録ですから、資格取得後すぐに開業を目指す方もいる様です。
独立開業の魅力
独立開業の魅力は、高収入を得られる可能性があることです。仕事の内容によっては年収数千万円も現実的な目標となり得ます。但し、この高収入の可能性は、自身の努力や顧客獲得の経営手腕やマーケティング能力に大きく依存するため、開業当初から安定した高収入を得られるとは限りません。
独立開業を選択した場合、業務内容、勤務時間、事務所の運営など、あらゆる面で高い自律性と裁量が与えられます。働き方の自由度が高いこともメリットとして挙げられます。自身の得意な分野や興味のある業務に集中し 、自分のペースで仕事を進めることができるため、ワークライフバランスを実現しやすいという魅力があります。しかし、この自由な働き方は、自己管理能力の高さと、全ての責任を自身で負う覚悟が必要となることを意味します。時にはクレーム対応など、精神的な負担を伴う可能性も多くありうる事を理解しておく必要があります。
多くの業務の中から専門分野を見つけてプロフェッショナルにならない限り、成功の夢は叶い難いでしょう。行政書士の業務範囲は大変幅広いのが特徴ですが、やみくもにあちこちの業務に手を出したのでは、どれも中途半端な知識で利益を出すことは通常は出来ません。
専門分野を絞り、どの様な顧客をターゲットにし、どの様に広告を打ち、どの様に営業をして売上に繋げるか。このビジョンなしに開業しても、利益どころか売上さえ上げる事は難しいでしょう。手続きを勉強する前に営業の勉強をしなければなりません。現代においては、インターネットを活用した集客が非常に重要であり、ホームページの作成やSEO対策、SNSの活用など、多岐にわたるマーケティング手法を駆使する必要がありますが、これらのスキルは、資格取得の勉強だけでは身につかないため、別途学習や実践を通じて習得していく必要があります。
また、コミュニケーション能力は必須です。お客様とのコミュニケーションは当然ですが、士業同士のコミュニケーションも大切です。税理士や司法書士との横のネットワークは行政書士の業務を行っていく中でとても重要であり、仕事の紹介にも繋がります。
独立開業の厳しさ
行政書士は食えない、仕事がない、低年収とするコメントも見かけます。それは、行政書士は他士業と比較して人数が多い=ライバルが多いのも事実ですが、多くの場合は営業力と技術力が伴っていないからです。簡単な手続き程敵は多く、価格競争が激しい為受託しても利益が出にくい、難しい手続きは高額だがノウハウが足りないのでリスクが高くて手が付けられない、これが食えない原因です。独立後1年目の年商が200万円~300万円はまだ良い方で、開業後半年は売上がゼロだった等、初期の収入の不安定さはよく語られています。
また、手続きについての法的知識は勿論必要ですが、法の解釈や判例なども含めて広く習得していく必要があり、実務は勉強よりも困難です。どの側面でどの様な壁にぶち当たり、それをどうやって乗り越えるかは、経験してみなければわからない事だらけです。
事務所勤務のメリット
実例と経験を基にした知識を得るには、やはり多くの事例を取り扱って来た諸先輩方と共に経験を積む事が近道であり、それが叶うのは事務所勤務なのではないでしょうか。関連した周辺知識も共に学ぶ事が出来ますし、複数カテゴリを取り扱う事務所であれば、ご自身の得意分野を見付け、その幅を広げる事もできるでしょう。将来的な独立開業を目指すうえでも大きなプラスになる事が期待出来ます。
行政書士の有資格者であれば、行政書士事務所への勤務は勿論、弁護士事務所でのアシスタントや、法人の設立等を得意としている司法書士事務所、相続関係を取り扱っている税理士事務所など、自身がこれから何を目指して行くかによって勤務先にも選択肢があります。
例えば行政書士法人TOTAL所属の行政書士ですと、許認可業務、会社設立、認可法人設立、遺言などの相続関連業務、国際業務などを専門分野とし、行政書士法人の他、グループ内の司法書士法人、税理士法人、社労士法人と連携して業務にあたっています。それぞれの業務に特性があり、個人の適性が問われます。最初は何を得意として良いか分からずに入社するスタッフも居ますが、性格や経験値、本人の希望などから、取り扱う業務を選択していきます。
事務所に所属して実務を学び、将来的には独立したい。そう考える方も多くいらっしゃるでしょう。事務所に勤務することで、先述した他士業とのネットワークを構築する機会が得られ、将来的に役立つ人脈を築くことができるのもメリットのひとつです。また、安定した基盤のもとで、体系的かつ段階的にスキルと経験を習得できる環境が提供されるので、着実にキャリアを積み重ねて行くことが出来ます。経験を積むことで、事務所内での昇進や、より責任のある業務を任される可能性もあります。将来的には、独立開業に必要なスキルや人脈を十分に蓄えた上で、独立という道を選択することも可能ですし、使用人行政書士として経験を積むというキャリアパスもあるでしょう。
まとめ
どちらの道を選ぶにしても、行政書士として成功するためには、継続的な学習意欲、高いコミュニケーション能力、顧客獲得の為のリサーチとマーケティング戦略、そして仕事に対する責任感は不可欠です。
行政書士事務所で働くことに興味や関心ある方はこちらの採用情報もぜひご覧ください。
皆様のご応募をお待ちしております。
執筆者

行政書士法人TOTAL
秋山 友樹子
行政書士。元マリンコントラクター勤務。主に許可申請を行う。
依頼者が新しいステージに進むためのサポートに尽力する。