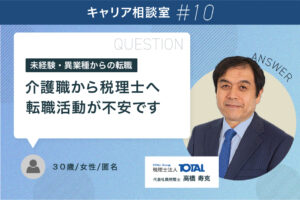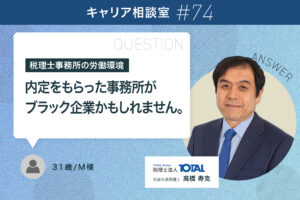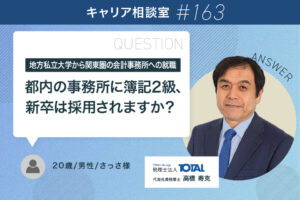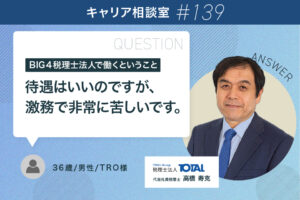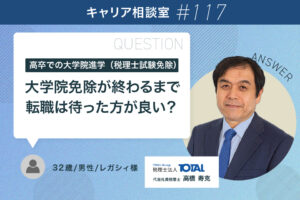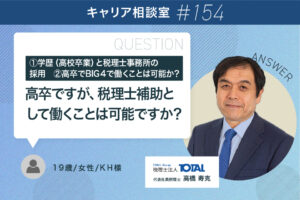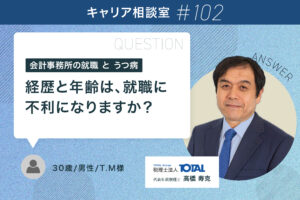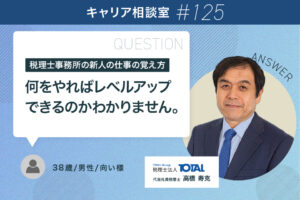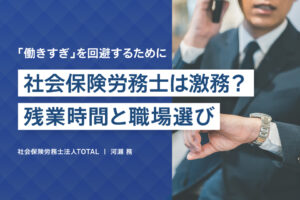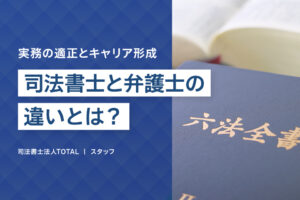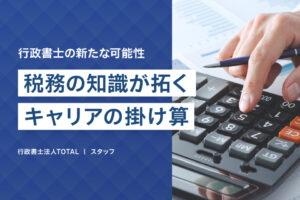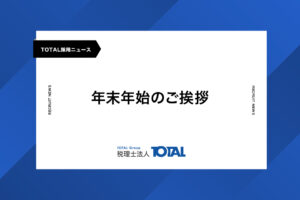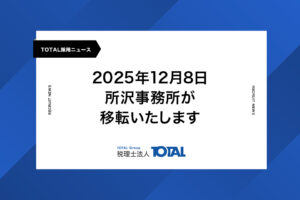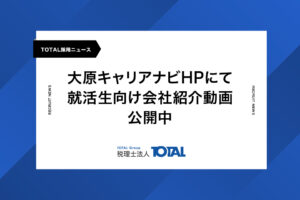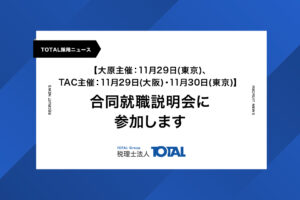キャリア相談室
会計事務所の転職(離職率、マニュアル化、新人教育、残業時間)
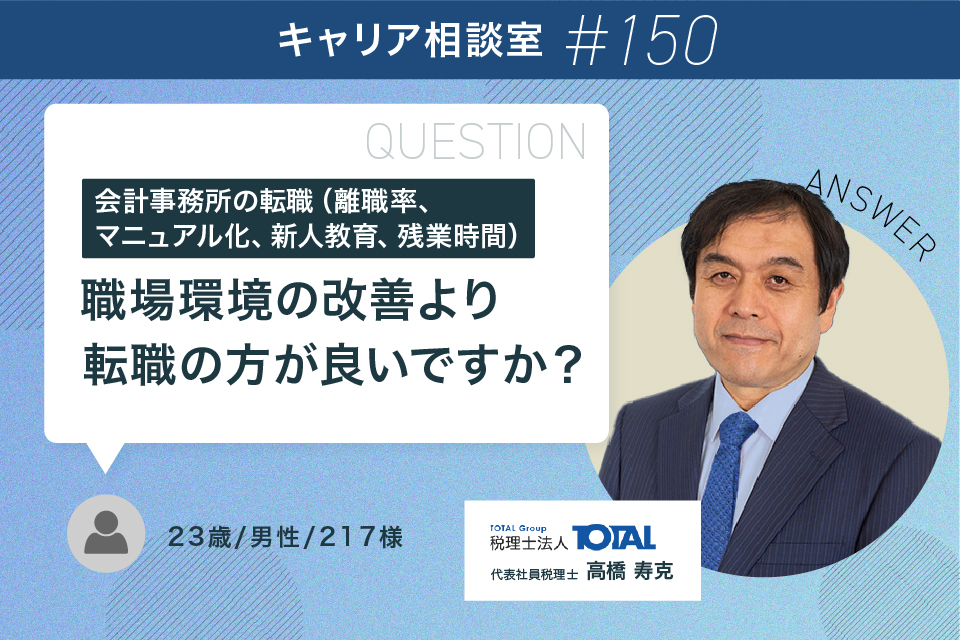
税理士事務所就職相談室の税理士 高橋寿克です。
「会計事務所の転職(離職率、マニュアル化、新人教育、残業時間)」
新規のご質問はここをクリック してください。
217様からのご質問です。
■年齢 23歳
■性別 男性
■資格 日商簿記2級
■職歴 接客業でアルバイトを数年
その後会計事務所に入社
■学歴 専門学校卒
■会計事務所経験 正社員 1年半ほど
■居住地 首都圏
はじめまして。よろしくお願い致します。
社会人経験、会計事務所経験が少ない故客観的判断がしづらいので
現在会計事務所に勤めはじめてもう少しで2年になります。
入所当時簿記検定は持っていましたが、社会人経験はなかったため
しかし事務所に対していくつかの不満点があります。
ひとつは「人の入れ替わりが激しい」ということ。
自分が入社した時にいたスタッフは既に全員退職しており、所長を
前任者が引継もなく辞めてしまい、所長から直接の指示がないまま
自分が最古参なだけでいろいろな仕事が回ってくるようになり、加
もう一つの不満点が「業務の非マニュアル化」です。
巡回業務、入力業務、決算業務など、どの業務も明確なマニュアル
自分の知らない仕事に取り掛かるときも、自分より長く勤めている
近い将来税理士試験の勉強を始めようと思っていますが、このまま
Q.
最近別の会計事務所に転職したほうがいいのかと考えるようになり
腐っても自分の人生、事務所の環境改善を待つのではなく、自らが
自分の勤める事務所の環境というのはどこの事務所でも同じような
A.
結論から先に言うと、会計事務所・税理士法人の働く環境は、バラバラです。
全国に5万以上、首都圏だけでも数万か所あれば、その数だけ労働環境は異なります。
働きやすさは、会計事務所によって対応が大きく違うところなので、217様が今度転職する際は、その前に色々な事務所で話を聞いてみて、自分に合う事務所を探しましょう。そのための参考情報を以下に書いてみます。
(1)会計事務所の離職率
人の入れ替わりが激しいということですが、さすがに1年半で最古参は珍しいでしょう。
業界の特徴として、受験生、主婦が多いため、他の業界よりは離職率が高い傾向があるのはやむを得ない面もあります。平均すると10%以上かもしれません(統計データがないので感覚的な言い方になります)
大手でも3年で知っている人がほぼいないというところもあります。人を大切にしないと働く人に選ばれなくなってきています。
会計事務所の離職率と規模による一般的な特徴については
を参考にしてください(ちょっと情報が古いかもしれません)。
会計業界も『人を大切にする業界』に代わってほしいと私は考えています。
===============================
税理士法人TOTALでは、年に一度、事業計画説明会で10年在職者に永年勤続表彰を行っています。長く勤めてくれるスタッフは税理士法人TOTALにとってありがたい、宝のような存在です。
確認しましたら、10年以上在籍者は16名、5年以上在籍者は実に63名でした。
たくさんのスタッフに支えられています。
今年の事業計画説明会は、200名を超えるグループの全社員が参加するのでコロナの影響もあり三密を避けるため、オンラインで行いました。
みなさん全員参加で、オンラインで活発に議論して
TOTALはどうあるべきかについて具体的な提言をたくさんいただきました。
ありがとうございました。
今後に経営に生かしていきたいと思います。
===============================
(2)業務のマニュアル化 と 新人教育
217様の事務所は巡回業務、入力業務、決算業務など、どの業務も明確なマニュアル
大変そうですね。
最近は、業務のマニュアル化は企業によっては当たり前のように行われています。
もとから進んでいたコンビニエンス・ストア業界はもちろん、
遅れているとされていた飲食、運送業界でも大手を中心にマニュアル化は進行中です。
会計業界は、以前は見て覚えろ、まねて覚えろ、盗め という業界でした。
今でも217様の事務所のようなところも一部はありますが、
最近では、きちんとマニュアル化が進んでいる税理士事務所・税理士法人も出現してきています。
これは、面接のときに聞いて、場合によってはそのマニュアルの一部を見せてもらえば大体わかります。すぐに出てこないようなら、マニュアルは整っていないと思ってもいいかもしれません。
===============================
税理士法人TOTALでは、業務ごとにマニュアルがあります。
未経験の新人のみなさんにとっては仕事がしやすいでしょう。
会計事務所経験者の方のうち、自分のやり方に固執する方は最初のうちはしんどいかもしれません。マニュアルはかなり合理的に作られています。しばらくマニュアル通りに進めてもらえれば、そのうちその意味も分かって、質の良い仕事を比較的簡単にできるようになります。
詳しくは、
税理士法人TOTALの採用ページ
<採用について> のQ.8を参照してください。
===============================
マニュアルがしっかりしていれば、新人教育はそれなりに安定します。
逆にマニュアルがないと、自分で調べなければならなくなり大変です。残業の増加は「働き方改革」に逆行しますし、ストレスの増加はコロナの時代に合いません。
所長の代わりにマニュアルが作れる未経験の新人はもちろんいません。
会計事務所の残業時間は、所長の考え方、事務所の置かれている状況によって大きく変わります。217様の事務所の所長は多忙で どうしたらいいか考える時間を取れていないのでしょう。トップの拡大意欲が、事務所の実力以上に強い事務所ではよく見られる現象でもあります。
もちろん、残業時間が多すぎると税理士試験の勉強時間を取ることはしにくくなるでしょう。
税理士試験前にどれだけ休めるかも事務所を選ぶ際の基準になるでしょう。休暇制度の有無ではなく、実際にどれくらいの方がどれだけ休んでいるかを面接の際に聞いてみてください。
217様も、あきらめずに仕事環境の整った会計事務所に転職して前向きに能力を高めていって、いつの日か社会の役に立つ、自分の仕事に誇りを持てる税理士になってください。
===============================
税理士法人TOTALでは、1分単位で労働時間管理をしており、一定上の残業をすると管理者(所長等)に注意喚起のメールが行く仕組みとなっています。
そのため、過大な残業をする受験生はあまりいません。
試験前は有給休暇や(特別の)試験休暇を取るスタッフが多いです。みなさんが頑張っておられるので、9年連続して官報合格者(税理士試験5科目合格)を輩出することが出来ています。
周りにも税理士試験を受験するスタッフがいるので刺激しあって結果を出せるのかもしれません。
今年は試験会場でTOTALのスタッフ同士が隣の席ということもあったそうです。
お客様は新型コロナウィルスの影響で自分の事業の先行きに不安を抱えており、スタッフへの相談はものすごく増えました。
誠実にその相談を聞いて、情報を提供しているので、スタッフはお客様に感謝されることが増えました。
特に労務に関する相談、人に関する悩み が多いのが今年の特徴です。
TOTALは、社労士も多数在籍しているので部門を超えて情報交換ができます。TOTALはこの時代でもお客様が今まで以上に増え続けています。
税理士は、将来消えてなくなる仕事だと揶揄された時期もありますが、
コロナによる不景気の影響はあまりなく、長く専門家として働けるこれからの時代、人生100年時代に合った仕事です。
オックスフォード大学や野村総研の研究よりも、お客様の反応の方が正しいでしょう。
最近では、保険会社、銀行(地方銀行に加えて都市銀行・メガバンクも)、営業会社等の大企業に在籍中の方からの転職も増えています。
「働き方改革」に加えてコロナの影響で在宅ワークが増え、転勤や営業ノルマに疑問を持つ人も増えているのでしょう。地元で密着して、夫婦が助け合って働ける会計業界の価値の見直しが行われています。
TOTALではそういった方の期待に応えていきたいと思っています。
===============================
新規のご質問はここをクリック してください。
インターネットで顔が見えない方に適切な回答をするために、 質問の書式にご協力いただけると幸いです。 情報が不足する場合には回答できないことがあることはご留意ください。
また、このサイトもありがたいことに皆様のご質問をいただき、事例が増えてきました。 ご質問の前に、同様な質問が無いかご確認いただけると幸いです。
「過去記事の検索」はこちらです。
執筆者

税理士法人TOTAL
代表社員税理士
高橋 寿克
千葉県船橋市生まれ。農家の12代目。税理士・行政書士・CFP®・医業経営コンサルタント。
開成高校、早稲田大学政治経済学部卒。
1999年 高橋寿克税理士事務所を開設。現在は全国17拠点に拡大したTOTAL Groupの代表として、税理士法人をはじめ、司法書士法人、社会保険労務士法人、行政書士法人を擁する。
徹底した業務の標準化やクラウドシステム(マネーフォワード、freee)活用で業務効率化を推進。「あなたと共に歩み、あなたと共に成長したい」を理念に日本一の総合士業事務所を目指している。