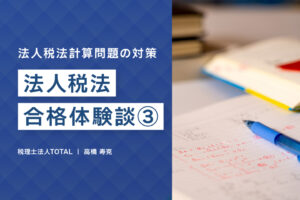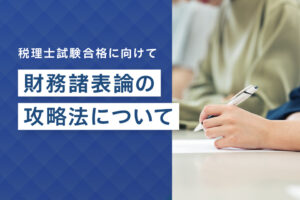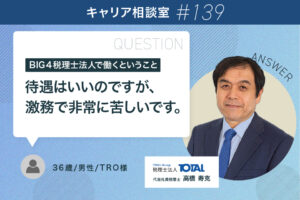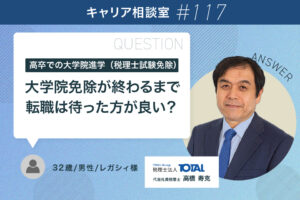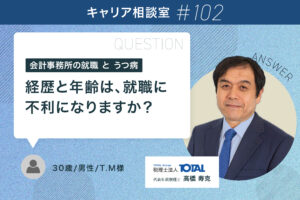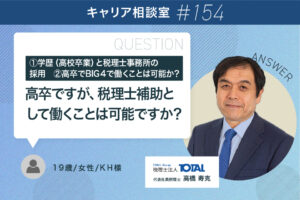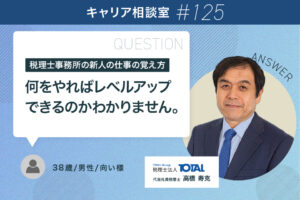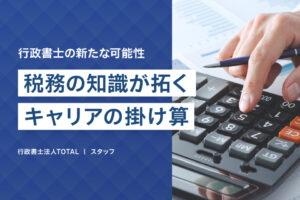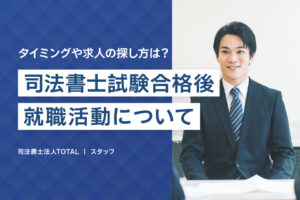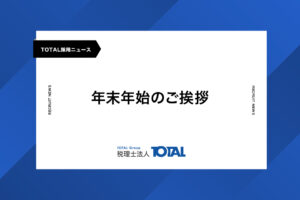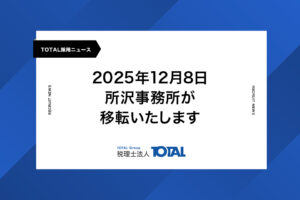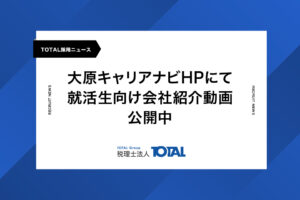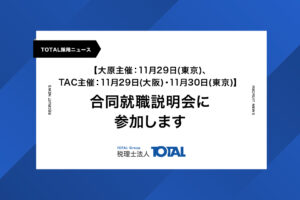キャリアコラム
税理士試験 科目別の特徴について
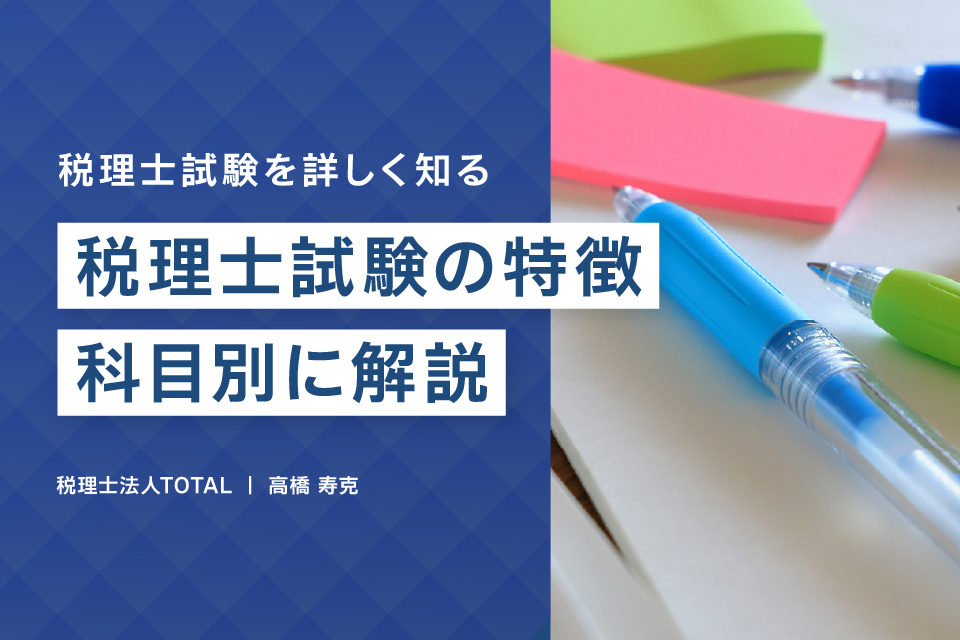
簿記論
税理士試験の基礎となる科目です。「簿記」とは、企業規模の大小や業種、業態を問わずに、日々の経営活動を記録・計算・整理して 経営成績と財政状態を明らかにする技能のことです。ほとんどの人がこの科目からスタートすると思います。税理士の実務にも直結する学問であり、「財務諸表 論」「法人税法」「所得税法」など他の試験科目にも関連してきます。日商簿記1級・2級を取得していると有利です。
財務諸表論
簿記は、「帳簿に記録付けする技術」ですが、財務諸表論は帳簿から「財務諸表」を作成する手順や、会計処理のルールを学ぶ科目です。「貸借対照表」「損益計算書」などが財務諸表と呼ばれるものです。簿記論と同じく、これも税理士試験の基礎となる科目です。 簿記論との関連が強いので、合わせて学習すると効果的です。
所得税法
所得税は、国の歳入のうち5分の1を占め、法人税や消費税など国税の中でも最も比重が高いものである。1年間のすべての所得から、あらかじめ定められた所得控除を差し引いた残りの金額を課税所得と言う。所得税は、個人の所得の中でも、この課税所得に税率を適用する。
所得金額は、給与所得や事業所得などその性質によって10種類に分類されている。それぞれの所得について、収入や必要経費の範囲、そして課税所得の計算方法が詳しく決められている。
所得控除は、個人的な事情を考慮して税負担を調整するという役割を担っている。例えば、医療費を支払ったときには、その負担を軽くするために医療費控除が認められている。また、配偶者や扶養家族がいる場合には、それぞれ配偶者控除や扶養控除が認められ、税の負担を軽くする。
また、条件さえ合えば、一旦納めた税金の一部が戻ってくるという還付制度もある。この場合は、納税者による手続きが必要となる。
所得税は、所得が多くなるにつれて段階的に税率が高くなる超過累進課税方式を採用している。これは、納税者がそれぞれの支払能力に応じて公平に税を負担すると同時に、行政サービスなどを通して行われる所得の再分配という効果がある。
納税は、原則として確定申告によって行うこととなっているが、サラリーマンの場合は毎月の給与やボーナスから源泉徴収される。
法人税法
法人とは法律の規定により「人」としての権利能力を付与された団体の事をいいます。株式会社や合資会社、宗教法人など沢山ありますが、それらが法人です。法人税は、法人の利益に対してかかる税金です。 所得税と同じようなイメージですが、計算方法は異なります。所得税法と同じく、税理士の実務ではほとんどの場合必要になります。 所得税法よりも法人税法の方が人気が高いです。
相続税法
相続税法は、相続税だけでなく贈与税も含まれます。相続税というのは、個人が亡くなり、その財産(家・土地・現金・有価証券など全ての財産)を引き継いだ 時にかかる税金です。相続税法は簿記の知識は必要なく、財産評価の知識や民法の知識が必要になってきます。「相続税」と「贈与税」はそれぞれ税金の計算方 法が異なりますが、違いを簡単に言うと「個人が亡くなった後に財産を引き継ぐ」のが相続税で、「生きている時に引き継ぐ」のが贈与税です。ただ、平成15 年度より「相続時精算課税制度」というものができたので、生前の贈与が相続にも直接影響する場合もあります。相続税を節税するためには、生前から計画を立 てなければなりません。生きている時から相続の話をするのは気がひけますけど。また、「相続税法」は実務でも活用頻度が高く、しかも単発の報酬が高いの で、相続をメインに営業している税理士さんもいるほどです。
消費税法
最も身近な税金です。消費税は「間接税」に分類されます。間接税とは納税義務者と税金を実際に負担する者が異なる税金をいいます。わた し達がお店で支払った消費税は、直接国へいきません。 お店が最終的に申告し、消費者から預かっていた消費税を納めます。 間接税といっても、負担しているのは消費者なので直接税だろうと結果は同じです。平成16年度から、事業者免税点が「3,000万円以下⇒1,000万円 以下」に引き下げらました。以前は売上3,000万円以下の場合は、消費税を申告しなくてもよかったのです。売上1,000万円以下というのは、事業を続 けられるギリギリのラインなので、ほどんどの事業主が消費税を納める事になりました。
酒税法
酒税は、アルコール飲料に対してかかる税金です。 消費税と同じ間接税で、購入者が支払います。ボリュームも少なめなので、学習しやすい科目といえますが、 税理士の実務で酒税法の知識を使うことは極めて稀です。ただ資格を取得したいだけという人には良いかもしれません。
国税徴収法
税金が払えない、滞納してしまっている!そのような場合の税金の徴収方法を規定している法律です。 財産の差し押さえや換価方法などを学びます
住民税
所得税、法人税が国税だったのに対し、住民税は地方税になります。
地方税とは都道府県・市町村に納める税金です。個人だけでなく、法人も住民税を支払わなければなりません。 住民税は前年の所得から計算されるため、所得税との関連が非常に強いです。所得税法の知識があった方が、効率よく学習できます。
事業税
住民税と同じく、事業税も地方税になります。 事業を営んでいる個人・法人に課税されます。 給与所得には課税されません。
固定資産税
固定資産税は、家や土地などの所有者に課税される地方税です。 税理士試験では固定資産税以外にも償却資産税も学びます。
執筆者

税理士法人TOTAL
代表社員税理士
高橋 寿克
千葉県船橋市生まれ。農家の12代目。税理士・行政書士・CFP®・医業経営コンサルタント。
開成高校、早稲田大学政治経済学部卒。
1999年 高橋寿克税理士事務所を開設。現在は全国17拠点に拡大したTOTAL Groupの代表として、税理士法人をはじめ、司法書士法人、社会保険労務士法人、行政書士法人を擁する。
徹底した業務の標準化やクラウドシステム(マネーフォワード、freee)活用で業務効率化を推進。「あなたと共に歩み、あなたと共に成長したい」を理念に日本一の総合士業事務所を目指している。